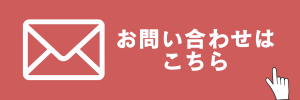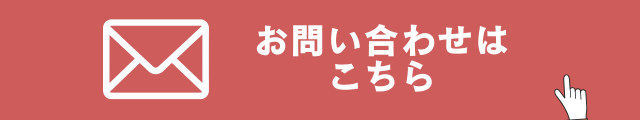OEM(受託製造)で健康食品やサプリメントを作ろうと考えたとき、多くの方が気にするのは 「製品そのものの価格」ではないでしょうか。
しかし、実際には 製品費用だけではなく、さまざまな “見えない費用”が発生します。
これを事前に把握していないと、「思っていたより費用がかさんでしまった…」といった想定外の出費につながることも少なくありません。
今回はOEM製造時に製品以外でかかる費用について詳しく解説します。
・どのような費用がかかるの?
・費用を抑える方法はある?
これからOEMを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
製品形態によって費用は大きく変わる
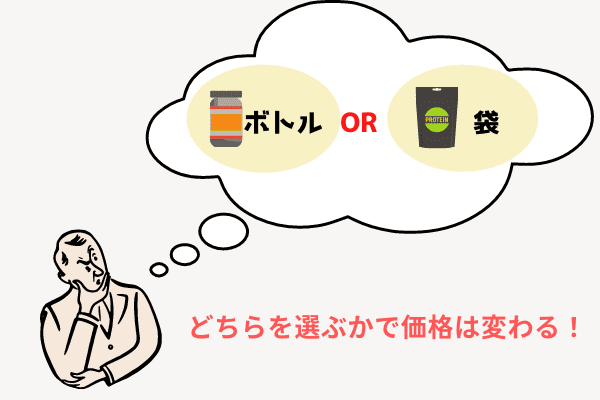 まず知っておきたいのは、製品形態によって製造工程や費用が異なるという点です。
まず知っておきたいのは、製品形態によって製造工程や費用が異なるという点です。
例えば、ダイエット向けのサプリを製造するとしましょう。
同じ「カプセル製品」でも、
工程:袋に充填 → 口をシールで閉じる(2工程程度)
工程:ボトルにラベル貼り → カプセル充填 → 緩衝材・シリカゲル投入 → 化粧箱に封入 → 封印シール貼り(5工程程度)
このように工程数が増える分、ボトル充填の方が製造費用は高くなるのです。
「なぜこの包装にするのか」を意識して選ぶことが、結果的にコストダウンにもつながります。
OEMで製品以外にかかる主な費用
ここからは、製品費用以外にかかる具体的な費用を順番に解説します。
なお、サンプル費や栄養分析費などは 初期費用 にあたるため、リピート製造時には基本的に発生しません。

① サンプル費用

OEM製造では、味や処方を確認するためのサンプル作成が必要です。
費用の有無は会社によって異なりますが、 相場は 2〜3万円程度。
※基本的には2〜3回の試作で内容が決定するケースが多い
※大幅な味変更や処方変更があれば、再度費用がかかる可能性あり
サンプル費を抑えるコツは、 事前のリサーチです。
市場に出ている商品を参考にして「どんな味」「どんな配合原料」が理想かを明確にしてから依頼すると、無駄な試作を減らせます。
栄養分析費
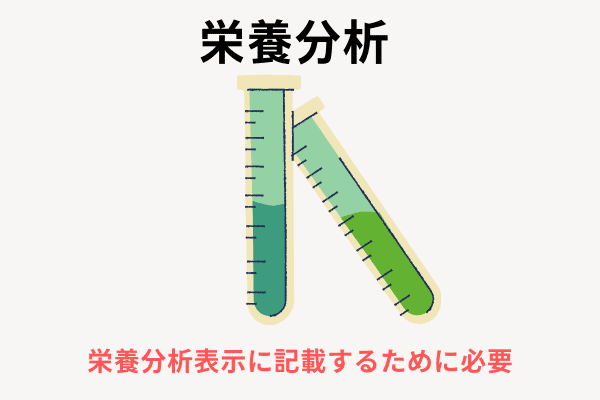
食品を販売する場合、パッケージには 栄養成分表示を記載することが義務付けられています。
基本的に必要なのは、エネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量です。
通常、表示が必須である基本的な栄養分析を行いますが、ビタミンや食物繊維などの特別な分析を行う場合は、別途費用がかかっていきます。
分析費用例(日本食品分析センター)
| 分析名 | 価格 | 分析項目 |
| 栄養成分表示基本セット | ¥21,000 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー、食塩相当量(ナトリウム) |
| 栄養成分表示セット (食物繊維:酵素-HPLC法) |
¥91,000 | 水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、糖質、食物繊維、エネルギー、食塩相当量(ナトリウム) |
| 食物繊維 | ¥70,000 | |
| ビタミンC(水溶性ビタミン) | ¥11,000 | 総アスコルビン酸(総ビタミンC) |
| ビタミンD(脂溶性ビタミン) | ¥29,000 | ビタミンD(ビタミンD2、ビタミンD3) |
| ルテイン | ¥14,000 | |
| 葉酸 | ¥15,000 |
※2025年8月現在
分析機関としては、日本食品分析センターが有名ですがやや高額。
コストを抑えたい場合は、以下の機関を利用するのも選択肢です。
・(一財)食品分析開発センターSUNATEC
・日本食品機能分析研究所
③ 資材費
資材費とは、袋・ボトル・ラベル・箱などの包装資材にかかる費用です。

・小ロットの場合 → ラベル貼り対応の方が初期費用を抑えやすい
どちらが正解というわけではなく、初期費用・ターゲット・販売価格・ブランディングを総合的に考えて選ぶことが重要です。

なお、 資材はOEM工場に任せることも、自社で手配することも可能です。
④ 送料
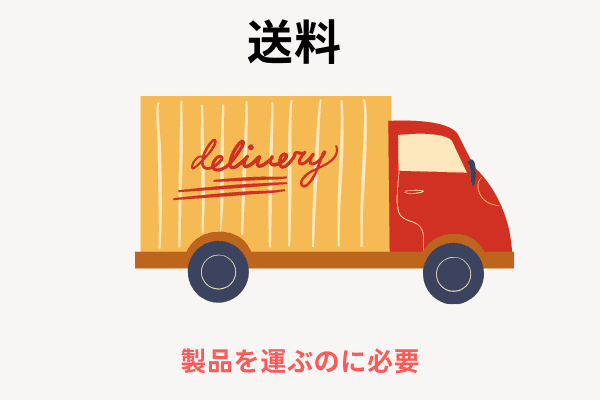
意外と見落とされがちなのが送料です。
近年は労働賃金やガソリン代の高騰により、 輸送コストも上昇傾向にあります。
工場からの見積もりでは 「送料込み」「送料別」のどちらなのかを必ず確認しましょう。送料別だった場合、想定以上に利幅が削られることもあります。
また、販売者側で運送会社と契約している場合は、自社で手配した方が安いケースもあります。
まとめ 〜製品費用以外も含めて総予算を考えよう〜
OEM製造では「製品そのものの価格」だけに注目しがちですが、 実際には サンプル費用・栄養分析費・資材費・送料 など、さまざまなコストがかかります。
特に初回製造時は、これらの 初期費用を計算に入れておかないと赤字リスクが高まります。
そのため、発注前に工場へしっかり確認することが非常に重要です。
初めてOEMに挑戦する方にも分かりやすくサポートいたしますので、ご不明点や具体的なご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!